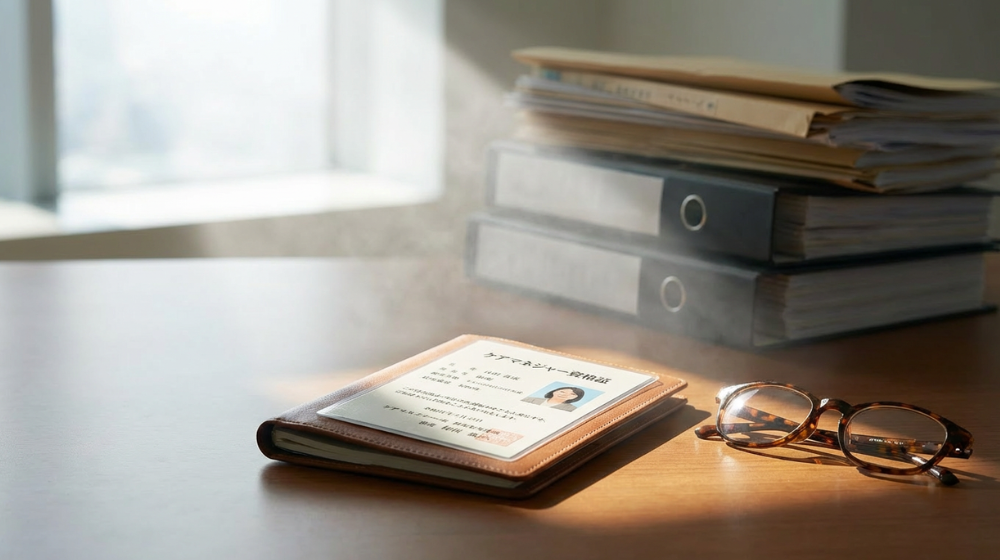記事公開日
【完全版】介護記録の書き方|例文30選とテンプレート・リスク管理まで徹底解説

介護記録の書き方1つで、日々のケアの質と業務効率は劇的に向上します。
なぜなら、記録は単なる作業ではなく、多職種連携を支える「情報共有」の要であり、利用者一人ひとりに最適なケアプランを導き出すための重要な根拠となるからです。
この記事では、記録の基本目的と5W1Hを用いた書き方のコツ、シーン別例文30選・実用テンプレート・監査対策まで、すぐに現場で活かせる知識をまとめました。
- 日々の記録業務に課題を感じている新人職員の方
- チーム全体の記録の質を底上げしたいリーダーの方
- コンプライアンスと業務効率化を両立させたい経営層の方
ぜひ最後までご覧ください。
介護記録の基本|なぜ記録は必要?目的と5つの必須項目

介護現場で日々作成される介護記録。
それは単なる業務日誌ではありません。
利用者一人ひとりの生活を支え、よりよいケアを実現するために欠かせない、重要な役割を担っています。
では、なぜ介護記録は必要なのでしょうか。
その根本的な目的と、記録に必ず含めるべき5つの必須項目について、具体的に解説します。
- 質の高いケアの実現(情報共有と連携)
介護は、日勤・夜勤の職員、看護師やケアマネジャーなど、多様な職種が連携しておこなうチームケアです。
自分が記録した内容は、次の担当者への重要な引き継ぎ情報となります。
利用者の日々の様子や心身の変化、実施したケアへの反応などを正確に記録・共有することで、どの職員が対応しても一貫性のある、質の高いケアを提供できます。 - 適切なケアプランの作成・見直し
ケアマネジャーが作成するケアプランは、利用者の心身の状態や生活状況に基づいた個別のアセスメントによって作成されます。
現場の職員が記録した日々の客観的な情報(食事摂取量・活動の様子・心身の変化など)は、ケアプランが利用者の現状に適しているかを評価し、必要に応じて見直すための重要な根拠となります。
つまり、適切なケアプランは、質の高い介護記録なしには成り立ちません。 - 利用者・家族とのコミュニケーション
介護記録は、利用者本人やその家族との大切なコミュニケーションツールです。
利用者の日々の様子や体調の変化を記録を通して家族に伝えることで、安心感と信頼関係を築くことができます。
また、家族が知らない施設での利用者の一面を共有したり、逆に家族から家庭での様子を聞き取ったりする際にも、記録が重要な役割を果たします。 - 介護サービスの証明とコンプライアンス
介護サービスは介護保険制度に基づいて提供されており、事業所は提供したサービス内容を適切に記録する義務があります。
記録は、介護報酬を算定するうえでの重要な証明書類となります。
厚生労働省が定める基準を遵守し、適切なサービス提供の証拠として記録を残すことは、事業所のコンプライアンス上、極めて重要です。 - 事故やトラブル発生時の証拠(法的根拠)
万が一、施設内で転倒事故や利用者間のトラブルが発生した場合、介護記録は当時の状況を客観的に証明する重要な「証拠」となります。
適切なケアがおこなわれていたことを証明し、職員や事業所を法的なリスクから守るための拠り所となるのです。
そのため、記録には憶測や感情を交えず、客観的な事実を正確に記載することが求められます。
【例文付き】わかりやすい介護記録を書くための3大原則とポイント

質の高い介護記録とは、専門職ではない家族や、他の職種の職員が読んでも「情景が目に浮かぶ」記録です。
曖昧な表現や個人的な感想だけでは、利用者の正確な状況は伝わりません。
わかりやすい記録を書くためには、次にある3つの原則をおさえましょう。
- 原則1:5W1Hで誰が読んでも状況がわかるように書く
- 原則2:客観的な「事実」と主観的な「解釈」を分けて書く
- 原則3:専門用語と略語は誰にでも伝わる言葉で書く
ここでは、これらの原則を具体的なOK/NG例文とともに、一つずつ詳しく解説します。
原則1:5W1Hで誰が読んでも状況がわかるように書く
介護記録の基本は、読み手が状況を明確にイメージできるよう書くことです。
この目的を達成するための効果的なフレームワークが「5W1H」です。
わかりやすい記録作成に役立つ基本ポイントを、5W1Hの枠組みで表にまとめました。
| 項目 | 意味・記載内容 |
|---|---|
| When(いつ) | 日時・時間帯 |
| Where(どこで) | 場所(居室、食堂、トイレなど) |
| Who(誰が) | 利用者本人、他の利用者、職員など |
| What(何を) | 起こった出来事、利用者の言動、ケアの内容 |
| Why(なぜ) | 背景や想定される原因(仮説は後述の「解釈」に区分) |
| How(どのように) | 具体的な様子・状況・対応方法(回数・量・時間で数値化) |
5W1Hを活用した記録では、When/Where/Who を先頭に固定することで場面設定が明確になります。
そのうえで、What/How を使い事実を具体的かつ客観的に記載することで、読み手が状況を正確にイメージしやすくなります。
一方、Why は推測を含む要素であるため、事実とは分けて「〜のご様子」「〜と思われる」「〜と感じた」といった表現を使い、それが職員の視点だとわかるようにしましょう。
【NG例文】
「おやつ前、Aさんが食堂で転倒される。」
これでは、正確な「いつ、なぜ、どのように」転倒したのかわかりません。
他の職員が状況を把握できず、原因分析や再発防止策の検討も困難です。
【OK例文】
(When)14:30頃、(Where)食堂のテーブルから、(Who)Aさんが、(Why)食器を片付けようと思われたのか立ち上がった際に、(How)足がもつれてバランスを崩し、(What)床に尻もちをついた。(強い衝撃はなく、その後も意識・呼吸に異常なし)。
このように5W1Hを意識しながら記録をすると、誰が読んでも具体的な状況と対応、その後の結果までを正確に把握できます。
原則2:客観的な「事実」と主観的な「解釈」を分けて書く
介護記録は、客観的な「事実」に基づいた記載が大原則です。
職員の個人的な感情や思い込み(主観)が入ると、情報の信頼性が損なわれ、適切なケアの妨げになる可能性があります。
- 事実:見たまま、聞いたままの出来事。数値化できる情報(時間・回数・量など)
- 解釈(主観):職員が事実から感じたこと、考えたこと、気づき
もちろん、専門職としての「気づき」は非常に重要です。
大切なのは、事実と解釈を明確に区別して書くことです。
解釈を記載する場合は、先ほどの原則1でもお伝えした Why の箇所、事実とは分けた「〜のご様子」「〜と思われる」「〜と感じた」といった表現を使い、それが職員の視点であることがわかるようにしましょう。
【NG例文】
鈴木さん、レクリエーションに乗り気ではなかった。
「乗り気ではない」は、職員の主観的な解釈であり、人によって捉え方が異なります。
【OK例文】
(事実)14:00からの集団体操の際、鈴木さんは「今日はやめておく」と発言し、ご自身の席で腕を組んで座っておられた。(解釈)いつもは積極的に参加されるため、午前中の受診で少しお疲れのご様子だったのかもしれない。
このように事実と解釈を分けて書くことで、記録の信頼性が高まり、他の職員も客観的な情報に基づいて適切な判断をくだせます。
原則3:専門用語と略語は誰にでも伝わる言葉で書く
介護記録は、介護職員だけでなく、看護師・ケアマネジャー・相談員・そして利用者本人や家族など、さまざまな立場の人が読みます。
そのため、一部の専門職にしかわからない専門用語や、その事業所だけで使われている内輪の略語の使用は避けましょう。
誰が読んでも正確に情報が伝わるように、平易な言葉で表現することが大切です。
【NG例文】
「Cさん、訪看のSTによるリハビリ後、BP測定。普段よりもかなり高めだったため、明日HPでNSが報告予定。その後、自力にて臥床された。」
「訪看」「ST」「BP」「HP」「NS」「自力」「臥床」などの言葉は、知らない人には意味が通じません。
【OK例文】
Cさん、訪問看護の言語聴覚士によるリハビリ(嚥下訓練)を受けられた。終了後に血圧を測定したところ、普段より高い値を示した。そのため、明日のかかりつけ病院受診時に、当施設の看護師から医師へ報告する予定となっている。血圧測定後、Cさんはご自身でベッドに横になられた。
【よく使われる専門用語・略語の言い換え例】
| 専門用語・略語 | 言い換え例 |
|---|---|
| VS(バイタル) | バイタルサイン(体温・脈拍・血圧・呼吸数など) |
| NPO(ニル・パー・オス) | 絶食、絶飲食 |
| デクビ | 褥瘡(じょくそう)、床ずれ |
| エスケープ | 徘徊、離設 |
| ワーカー | 介護職員 |
多職種がスムーズに連携し、チームとして質の高いケアを提供するためにも、「誰にでも伝わる記録」を常に意識しましょう。
【応用編】SOAP(ソープ)形式での介護記録の書き方と具体例

日々の記録に慣れてきたら、より専門的で構造的な記録手法の「SOAP(ソープ)形式」に挑戦してみましょう。
SOAP形式はもともと医療現場で使われてきた記録方法で、情報を整理し、問題解決につなげるための優れたフレームワークです。
この形式で記録すると、ケアの根拠が明確になり、看護師やリハビリ専門職など他職種との連携もスムーズになります。
SOAPは、次の4項目の頭文字をとったものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| S(Subjective:主観情報) | 本人や家族の訴え・感想・痛みの表現など |
| O(Objective:客観情報) | 観察・測定データ・事実(回数・量・時間・部位・バイタル等) |
| A(Assessment:評価) | SとOをもとにした職員の見立て・分析・リスク判断 |
| P(Plan:計画) | 対応・次回方針・ケアプラン反映・家族/看護師への報告など |
それぞれの項目に何を書くのか、具体的なケースを例に挙げてみていきましょう。
【S:主観的情報 】(Subjective)
利用者の訴えや家族から聞いた話など、本人の主観的な情報を記載します。
本人の言葉は「」を用いて、そのまま記述するのがポイントです。
【Sの記述例】
Aさんより「夕食後から右膝がズキズキ痛む」との訴えあり。
【O:客観的情報 】(Objective)
職員が観察したこと、測定した数値など、客観的な事実を記載します。
バイタルサインや食事摂取量、表情、皮膚の状態など、五感で得た情報を具体的に書きます。
【Oの記述例】
- 痛みを訴える際、顔をしかめている。
- 右膝を触診したが、熱感や腫れ、発赤はみられない。
- 歩行時、右足を少し引きずる様子がみられる。
- バイタル:体温36.5℃、血圧130/80mmHg、脈拍72回/分。
- 本日のレクリエーション(風船バレー)には意欲的に参加されていた。
【A:評価】 (Assessment)
S(主観的情報)とO(客観的情報)を統合し、専門職としてどのように考え、判断したかを記載します。
記録のなかでも最も専門性が問われる部分です。
何が問題で、その原因は何かを分析します。
【Aの記述例】
S情報とO情報から、レクリエーションでの活動による一時的な膝の痛みではないかと思われる。発熱や外傷はみられず、バイタルも安定しているため、現時点での緊急性は低いと、現場にいた主任看護師と機能訓練指導員含め、緊急性はないと判断。
【P:計画】 (Plan)
A(評価)に基づき、今後どのようなケアをおこない、どのように経過を観察していくかという具体的な計画を記載します。
短期的な計画(Immediate Plan)と、長期的な計画(Long-term Plan)に分けて書くと、よりわかりやすくなります。
【Pの記述例】
<短期計画>
- 居室のベッドで安静にできるよう声かけをおこない、楽な姿勢がとれるようクッションで調整する。
- 30分後と1時間後に痛みの程度に変化がないか確認する。
- 痛みの増強や他の症状が出現した場合は、速やかに看護師に報告する。
<長期計画>
明日以降も痛みが続くようであれば、機能訓練指導員と情報共有し、運動プログラムの見直しを検討してもらう。
このようにSOAP形式で記録を整理することで、「利用者の訴え」→「事実の確認」→「専門職としての評価・判断」→「今後の具体的な対応」という一連の流れが明確になり、誰が読んでも論理的でわかりやすい記録を作成できます。
【シーン別】すぐに使える介護記録の書き方と例文集

介護記録の基本原則を理解したら、次は日々の具体的なシーンでどのように書くかを学びましょう。
現場で頻繁に遭遇する場面での記録は、ポイントさえおさえれば、誰でもわかりやすく書けるようになります。
ここでは、次の4つのシーン別に、記録のポイントとすぐに使える豊富な例文を紹介します。
- 食事・水分補給・服薬の記録
- 入浴・整容・排泄の記録
- 夜勤・巡視の記録
- 機能訓練・レクリエーションの記録
自分の業務と照らし合わせながら、明日からの記録作成に役立てましょう。
食事・水分補給・服薬の記録
食事の記録は、利用者の栄養状態や健康状態を把握するための重要な情報源です。
食事量だけでなく、食事中の様子や義歯の適合状態など、多角的な視点で観察し記録しましょう。
【記録のポイント】
- 食事摂取量:「半分くらい」といった曖昧な表現ではなく、「主食8割、副食5割摂取」のように具体的に記載する。
- 食事中の様子:むせや咳き込みの有無、食事にかかる時間、介助の必要性などを記録する
- 水分量:どのくらいの量を飲んだか(例:お茶を150ml)を記録する
- 服薬:確実に服薬できたか、拒否はなかったかを記録する
【例文】
<例文1:食事が全量摂取できた場合>
12:15 昼食。配膳すると「おいしそうだね」と笑顔で話される。主食・副食ともに全量摂取。むせやこぼしはみられず、ご自身で綺麗に召し上がる。食後のお茶も150ml飲水された。昼食後薬も「お願いします」手を差し出され、確実に内服された。
<例文2:食事の進みが悪い場合>
18:10 夕食。おかず(煮魚)を一口食べた後、箸が止まる。「あまり好きじゃないな」と小声で話されたため、「お口に合いませんでしたか。ご飯だけでもいかがですか」と声かけするも、それ以上は進まず。主食2割、副食1割の摂取。水分(お茶)は100ml飲水。
入浴・整容・排泄の記録
入浴や排泄に関する記録は、利用者の尊厳に関わるデリケートな情報です。
プライバシーに最大限配慮しつつ、健康管理に必要な情報を客観的な事実として正確に記録することが求められます。
特に皮膚の状態観察は重要です。
【記録のポイント】
- 入浴時の様子:表情や言動、疲労の有無、洗身・洗髪など自分でできたこと、介助したことを記録する
- 皮膚の状態:発赤・湿疹・乾燥・創傷の有無などを具体的に観察し、部位と共に記録する
- 排泄状況:トイレ・ポータブルトイレ、オムツなど、どこで排泄したかを明記し、回数・量・性状(色、形)を客観的に記録する
- プライバシーへの配慮:「便失禁あり」→「多量の軟便あり、リハビリパンツ交換」のように、客観的な表現を心がける
【例文】
<例文3:入浴時の記録>
14:00 入浴介助。湯船に入ると「あー気持ちいい」と笑顔がみられる。洗身・洗髪は職員が介助。背部に2cm程の掻き傷があるが、化膿や熱感はなし。湯上り後も「さっぱりした」と満足された様子。
<例文4:トイレでの排便記録>
10:20「便が出そう」との訴えあり、トイレへ誘導。手すりを使用してスムーズに移乗される。普通量の黄褐色普通便あり。排泄後はご自身で後始末をされた。
夜勤・巡視の記録
夜勤中の記録は、利用者の睡眠状態や夜間の様子を日勤帯の職員に伝えるための重要な役割を担います。
特に変化がなくても「変化なし」と記録することで、穏やかに過ごせていたという情報になります。
【記録のポイント】
- 睡眠状態:スムーズに入眠できたか、中途覚醒の有無、いびきの状態などを記録する
- 巡視時の様子:呼吸状態、体位、表情などを観察する
- 夜間の訴えやトイレ介助:ナースコールへの対応内容や、夜間のトイレ介助の状況を5W1Hで記録する
【例文】
<例文5:穏やかに睡眠している場合>
2:00 訪室巡視。静かに寝息を立てて入眠されている。呼吸は穏やかで、苦痛な表情などもみられない。室温25℃、湿度50%で環境も良好。
<例文6:中途覚醒があった場合>
3:15 訪室すると、ベッド上で目を開けておられた。「眠れないの」と話されたため、背中を5分ほどさする。その後、「少し落ち着いたわ」と話され、徐々にうとうとされ始める。
機能訓練・レクリエーションの記録
機能訓練やレクリエーションの記録は、利用者の身体機能やQOL(生活の質)の維持・向上を評価するための大切な資料です。
活動への参加状況だけでなく、他者との交流の様子や本人の表情、発言などを記録しましょう。
【記録のポイント】
- 参加状況:自ら参加したか、促されて参加したか、参加時の意欲などを記録する
- 活動中の様子:具体的な活動内容、表情(笑顔、真剣な顔など)、他の利用者や職員とのやり取りを記録する
- 心身の変化:「以前より腕が上がるようになった」「他の利用者と楽しそうに会話する場面が増えた」など、ポジティブな変化を記録する
【例文】
<例文7:集団レクリエーションの記録>
15:00 風船バレーに参加。職員の声かけに「やるよ」と意欲的。隣のBさんとパスを交換し合い、「上手だね」「そっちもね」と笑顔で会話されている。ゲーム中は何度も立ち上がって風船を追いかけ、活発に動かれていた。
<例文8:個別機能訓練の記録>
10:30 機能訓練指導員と平行棒内での立位・歩行訓練を実施。以前は5mで疲労がみられたが、本日は10mまで安定した足取りで歩行可能であった。訓練後は「前より歩けたね」と達成感のある表情をされていた。
シーンに応じた記録のポイントと具体的な表現をおさえることで、誰が読んでも状況が目に浮かぶような、質の高い記録を作成できます。
記録はケアの質を左右する重要な業務だからこそ、日々の実践でスキルを磨いていきましょう。
【業務効率化】明日から残業を減らすためのテクニックとツール

質の高い記録の重要性は理解していても、日々の業務に追われ、記録作成に時間がかかりすぎている、と感じている方も多いのではないでしょうか。
記録業務の負担を軽減することは、ケアに集中できる時間を増やし、残業を減らすことにも直結します。
ここでは、日々の記録業務を効率化するための具体的なテクニックと、すぐに現場で活用できるツールを紹介します。
手書きでも効率アップ!記録時間を短縮するコツ
現在も手書きで記録をおこなっている事業所は少なくありません。
手書きならではの良さもありますが、少しの工夫で記録時間を大幅に短縮することが可能です。
【ポケットサイズのメモを活用する】
ケアの合間に、利用者の様子や発言で気になったことを「キーワード」だけでもメモしておきましょう。
「14:10 Bさん 食堂で笑顔」「Cさん 水分 100ml」のように断片的でも構いません。
業務の最後にまとめて記録を書こうとすると、詳細を思い出せずに時間がかかってしまいます。
リアルタイムのメモが、後の清書時間を大きく短縮します。
参考に、下記のようなメモの取り方をみていきましょう。(施設介護の場合)

1)左上「(予定)」=1日の主な動き
- 朝のミーティングや連絡ノートで集めた利用者の予定を一覧化
- 凡例:受=受診/カット=ヘアカット/面=家族面会/外出=本人外出
- ねらい:誰に何の対応が必要かをひと目で把握→人員配置・準備物の抜け漏れ防止
2)右上「(フロ)」=本日の入浴者リスト
- AM(午前)/PM(午後)に分け、上から入浴順
- ねらい:タオル・更衣・皮膚観察の段取りが立てやすい(申し送りや物品準備もスムーズ)
3)中央~下段「12 …」=昼食後ケアの即メモ
- 「12」は12時台の意味
- 記号で排泄状況を即時に可視化:
◎=排尿あり ✓=排便あり 〇=排泄なし - 口腔ケアは全員実施のため、あえて記載を省略(記録のムダ削減)
- ねらい:ケア直後に数秒で記録→のちの介護記録の清書が速い・抜け漏れゼロ
4)特記事項の書き方(例:「12:45 カツさん」)
- 具体時刻+出来事+対応+報告先まで短文で書く
運用ルール(6つだけ)
- ケアが終わったら20~30秒で1行メモ(1件1行)
- When/Who/What/Howだけを書く(Why「原因推測」は、後の清書で正式記録する)
- 利用者の名前は略す+「さん(様)」をつける(メモを落とした時のトラブル予防)
- 特記事項は分単位の時刻と報告先を必ず記載
- 退勤前にメモ→正式記録へ転記
- その日のメモは、その日に処分(タスクを明日に残さない)
メモ→正式記録への変換例
- メモ:「12 森さん ◎」
→ 記録:12:10 トイレ誘導。排尿あり。口腔ケアはご自分でされた。 - メモ:「12 守さん ◎✓」
→ 記録:12:20 トイレ介助。排尿あり・排便あり(普通便)。口腔ケアで仕上げ磨き実施。 - メモ:「12:45 カツさん(特記)」
→ 記録:12:45 腰痛訴え(+)、熱感(-)。看護師へ報告し、2名でカツさんの腰痛状態をチェックする。強い痛みではないが、念のため全介助にて車いす→ベッド移乗。
この「メモから清書」という一手間が、記録業務の効率を飛躍的に高め、記録作成にかかる時間を大幅に短縮させます。
2. 施設内で「よく使う言葉」を統一する
食事の「全量摂取」「半分摂取」や、巡視時の「訪室時、入眠中」、排便なら利用者のこぶし大で「中量」、こぶし大より多ければ「多量」など、頻繁に使う表現をあらかじめ統一し、職員間で共有しておきましょう。
これにより毎回文章を考える手間が省け、誰が記録してもわかりやすい記録になります。
すぐに使える!介護記録テンプレート(ダウンロード可)
ゼロから文章を考えると時間がかかりますが、テンプレートがあれば、必要事項を埋めてくだけで、質の高い記録を効率的に作成できます。
【紹介①:手書き用の公式テンプレート】
厚生労働省が推進する「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」の公式Webサイトでは、介護記録の様式例が公開されています。
公的な資料であり信頼性が高く、現場の実態に即した内容になっているため、ダウンロードして印刷すれば、すぐに日々の記録に活用できます。
手書き記録の標準フォーマットとして、活用しましょう。
【紹介②:アプリによる入力の推奨】
記録業務の負担を根本から解決し、大幅な効率化を実現するなら、アプリの導入が最も効果的です。
「ファーストケア・ポータブル」は、経過記録・バイタル・入浴・排泄など、日々の記録を簡単に入力できる機能が充実しており、現場職員の業務負担を大きく軽減します。
- 専用アプリで「その場」記録
利用者のそばでケアをしながら、その場で記録が完結。
事務所に戻ってからの転記作業は不要です。 - 定型文や音声入力で入力の手間を削減
よく使う文章を登録しておけば、タップ1つで入力完了。
音声入力にも対応しており、手入力の手間を省きます。 - リアルタイムで情報共有
入力した記録は即座にチーム全体に共有されるため、申し送りもスムーズ。
ケアの質向上にもつながります。
「本当に使いやすいの?」「どのような画面で記録するの?」といった疑問は、実際の画面をみるのが一番です。
下記の無料カタログでは、経過記録・入浴・排泄表といった具体的な記録画面の画像や、詳細な機能説明を確認できます。
自分の職場の記録業務がどう変わるか、まずは資料をみてイメージしてみましょう。
【リスク管理】監査とトラブルから自分と職場を守る記録術

介護記録は、単に日々のケアの内容を記録するためだけのものではありません。
行政による実地指導(監査)や、万が一の事故・トラブルが発生した際に、その対応の正当性を証明する「法的な証拠」としての重要な側面も持っています。
不適切な記録は、思わぬトラブルを招きかねません。
ここでは、監査や訴訟などのリスクから組織と自分自身を守るための、客観的で正確な記録の書き方を解説します。
【NGワード一覧】介護記録で使ってはいけない言葉を学ぼう
何気なく使っている言葉が、実は利用者の尊厳を傷つけたり、記録の客観性を損なったりしていることがあります。
職員の主観や思い込み、侮辱的な表現は、記録の信頼性を著しく低下させるため、使用してはいけません。
代表的なNGワードと、その言い換え例をまとめました。
日々の記録で使っていないか、自己チェックをしてみましょう。
| NGワード(不適切な表現) | OKな表現(客観的で丁寧な言い換え) | ポイント |
|---|---|---|
| 徘徊(はいかい) | 「落ち着かないご様子で廊下を歩かれている」 「居室と食堂を行き来されている」 |
「徘徊」という言葉には否定的な意味合いが含まれるため、行動の事実をそのまま記載 |
| 暴言・暴れる | 「『家に帰る!』と大きな声で訴えがあった」 「介助の際に手を振り払う動作がみられた」 |
利用者の言動を具体的に描写し、「暴れる」ではなく、どのような行動があったかを客観的に書く |
| 拒否される | 「更衣をお勧めしたが『今はいい』とのお話あり」 「ご本人の意思表示により、本日の入浴は見送る」 |
利用者自身の意思を尊重した表現にし、「拒否」と断定せず、利用者の言葉や選択をそのまま記録 |
| ~させる | 「~していただく」「~をお勧めする」 | 「食べさせる」「入浴させる」といった使役表現は、上下関係を想起させ不適切なため、敬意を払った表現を心がける |
| (診断のない病名) | 「腹痛の訴えあり」「皮膚に発赤がみられる」 | 医師の診断がない限り、「胃腸炎」「褥瘡(じょくそう)」といった病名の記載はNG(観察した状態をそのまま記録) |
| わがまま・しつこい・言うことを聞かない | 「繰り返し『〇〇してほしい』と要望があった」 | 職員の主観的な感情や評価(わがまま、しつこいなど)は記録に含めず、客観的な事実のみを記載 |
| ~のようだ たぶん~だろう たくさん・すこし |
「~という言動がみられる」 「~と考えられる」(根拠を添えて) 「主食を8割摂取、水分100ml」 |
憶測や個人の感想になるため、事実と異なる可能性がある(人によって解釈が異なる) |
他にもいくつか紹介します。
介護記録では、レッテル語・曖昧語・心情推測は避け、行動+頻度+状況で言い換えましょう。
- 不穏 → 立ち上がりを5回試み、周囲を見回す
- 徘徊 → 14:05~14:15 食堂と廊下を往復歩行(約30m×3往復)
- 暴言 → 「帰る」「触らないで」と2回発言(大声)
- 暴力 → 右手で職員前腕を1回叩く(強度:軽度、皮膚所見なし)
- 寝たきり → ベッド上安静が継続、本日離床0回
- 認知症が進行 → 5分後の再質問で内容想起できず、メモで再説明
- 食事しっかり → 全粥200g中150g/味噌汁100ml中50ml
- 問題なし/安定 → 睡眠連続4時間、巡視2回、離床なし
- 見守り強化 → 15分ごとに訪室、チェックリスト使用
- 便失禁 → 多量の軟便あり、リハビリパンツ交換・皮膚保護実施
迷った場合は「回数・量・時間・部位」を具体的に記載し、主観的な判断を書く際は必ず根拠やデータと一緒に示しましょう。
【暴言・暴力・ヒヤリハット…】トラブル場面での記録方法を知ろう
利用者からの暴言や暴力、あるいは転倒などのヒヤリハットや事故が発生した際は、特に冷静かつ客観的な記録が求められます。
感情的にならず、事実を5W1Hに沿って淡々と記録することが、後の対応をスムーズにし、職員自身を守ることにもつながります。
【記録のポイント】
トラブル場面の記録では、5つのポイントをおさえましょう。
| 記録のポイント | 内容 |
|---|---|
| ①時間の正確な記録 | 発生時刻、対応開始・終了時刻を分単位で記録 |
| ②発言の引用 | 利用者の暴言などは、解釈を加えず「」を用いてそのまま記載 |
| ③行動の具体的描写 | 「叩かれた」ではなく、「右手で職員の左腕を3回叩かれた」のように具体的に書く |
| ④対応と結果の記録 | どのような対応(傾聴、他職員への応援要請など)をし、その結果どうなったかを時系列で記録 |
| ⑤身体状況の確認 | 職員や利用者に外傷がないかを確認し、その結果も必ず記録 |
具体的な状況を想定した「例文」をみていきましょう。
【例文9:利用者からの暴言があった場合】
14:30 Aさんがお茶をこぼされ、職員が新しいおしぼりをお持ちした際、突然「こんなものいらない、馬鹿にするな!」と大声で発言あり。おしぼりを床に投げつける動作がみられた。職員が「何かお気に召さないことがありましたか?」と尋ねると、興奮された様子で同様の発言を繰り返される。5分ほど傾聴に徹したところ、徐々に落ち着きを取り戻された。
【例文10:利用者からの暴力があった場合】
15:10 居室にて、Bさんの更衣介助をおこなおうとした際、Bさんが突然立ち上がり、「触るな!」と大きな声で発言される。同時に、右手で職員の左腕を強く1回叩かれた。すぐにBさんから距離を取り、「驚かせてしまい申し訳ありません。少しお休みしましょうか」と声かけをおこなう。Bさんは「一人でできる」と興奮されたご様子だったため、応援の職員を要請。2名体制で対応し、ご本人の意思を尊重して一旦更衣介助は見合わせることとした。看護師に状況を報告し、職員の左腕に打撲痕や発赤がないことを確認。Bさんご本人にもお怪我がないことを確認済み。
【例文11:転倒事故(ヒヤリハット)があった場合】
10:20 食堂から居室へ移動中、Aさんが「じゅうたん」の縁につまずき、前方へ転倒される。すぐに駆け寄り、意識レベル、バイタルサインに異常がないことを確認。ご本人より「お尻を打った」との訴えあり。看護師へ報告し、両名で外傷の有無を全身にわたり確認。左殿部に軽度の発赤がみられるが、腫脹や熱感、骨折の疑いはなし。立ち上がり、歩行状態も普段と変わりないことを確認した。(詳細:ヒヤリハット報告書)
このように、トラブル発生時には感情的にならず、事実を客観的かつ時系列で記録することが極めて重要です。
正確な記録は、その後のケアプランの見直しや再発防止策の検討に欠かせないだけでなく、万が一の事態において事業者と職員自身を守るための重要な証拠となります。
【訪問・通所・施設別】記録のポイントを理解しよう
提供するサービスの形態によって、介護記録で求められる視点や重点的に記録すべき項目が異なります。
それぞれの特性を理解し、ポイントをおさえた記録を心がけましょう。
1. 訪問介護の記録ポイント
限られた時間内で決められたサービスを提供する訪問介護では、「いつ、誰が、何をおこなったのか」を明確に記録し、サービス提供の証拠とすることが最も重要です。
また、利用者宅での様子や前回訪問時からの変化を、サービス提供責任者やケアマネジャーに正確に伝える重要な役割も担っています。
【例文12:訪問介護】
10:00~10:45【生活援助】掃除機による居室・廊下の清掃、トイレ清掃を実施。11:00~11:30【身体介護】昼食の準備、配膳。ご自身で主食・副食ともに全量摂取される。服薬も確認。本日、郵便物が3通届いていることをお伝えした。
2. デイサービス(通所介護)の記録ポイント
デイサービスの記録では、家庭ではみられない「日中の活動の様子」を家族に伝える重要な役割があります。
機能訓練の成果や、他利用者とのコミュニケーション、レクリエーションへの参加状況など、集団生活における利用者の表情や言動を具体的に記録することが求められます。
【例文13:デイサービス】
午後の集団体操に意欲的に参加。以前は腕が肩までしか上がらなかったが、本日は耳の横までスムーズに上げられた。隣の席のCさんと談笑されるなど、終始穏やかな表情で過ごされていた。
3. 施設介護(特養など)の記録ポイント
24時間365日の生活の場である施設では、日中だけでなく夜間も含めた継続的なケアが必要です。日勤・夜勤の職員間でのスムーズな情報共有が不可欠であり、食事・水分・排泄・睡眠といった生活全般のデータを蓄積し、長期的な視点で利用者の心身の変化を捉えることが重要になります。
【例文14:施設介護】
2:00 定時巡視。訪室時、静かに入眠されている。呼吸状態は穏やかで、苦痛な表情もみられない。昨夜は2度の中途覚醒があったが、今夜は朝まで深く眠れている様子。室温25℃、湿度50%で環境も良好。
このように、リスク管理の視点を持った記録術は、単なる文章作成のテクニックではありません。
記録技術は、利用者の尊厳を守り、提供したケアの正当性を証明するだけでなく、介護のプロフェッショナルとして自分自身と職場を守るために欠かせないスキルです。
今回学んだNGワードの言い換えと、客観的な事実記載を日々の記録で意識しましょう。
その積み重ねが、万が一の際に自分を支える、信頼性の高い「証拠」になります。
【特別資料】介護記録の書き方をさらに実践したい方へ:例文30選を無料ダウンロード

この記事で紹介した基本例文に加え、さらに多様な状況に対応できる「シーン別 介護記録の例文30選」を、特別資料としてご用意しました。
実際の介護現場で記録を書く際、表現に迷う方に最適です。
いざという時に参考にできる文例集が手元にあると、表現の幅が広がり、よりスムーズに記録業務を進められます。
ぜひダウンロードして、日々の業務にお役立てください。
介護記録の書き方に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、介護記録に関して多くの人が抱く素朴な疑問から、一歩踏み込んだ質問まで、よくある質問をQ&A形式でまとめました。
- Q1. 記録の保管期間に決まりはありますか?
-
A1. 介護サービスの提供記録は、原則として「完結の日から2年間」の保存が求められます(自治体によっては条例で5年間を求めるケースあり)。
一方、介護給付費の請求関係書類は5年間の保存が基準です。
医療的な診療録(カルテ)は医師法により5年間の保存義務があります。
運用は自治体の指導(実地指導・集団指導)に従い、事業所の規程に明記しましょう。
<p参考:厚生労働省介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」「診療録の保存年限に係る現行法令上の規定について」
参考:福山市ホームページ「【記録の整備】『完結の日』の解釈について」 - Q2. 記録はPC(パソコン)と手書き、どちらがいいですか?
-
A2. それぞれにメリット・デメリットがあり、事業所の方針によって異なります。
施設の規模や職員のITスキル、導入コストなどを総合的に判断して選ぶことが重要です。PC入力と手書きのメリット・デメリット PC(介護ソフト・アプリ) 手書き メリット ・情報共有が迅速かつ正確
・記録の検索やデータの分析が容易
・文字が読みやすく、統一感が出る
・ペーパーレス化で保管スペースが不要・導入コストがかからない
・停電やシステム障害時でも記録できる
・PC(パソコン)操作が苦手な職員でもすぐに書ける
・手書きならではの温かみが伝わる場合があるデメリット ・導入や運用にコストがかかる
・PCやタブレット操作の研修が必要
・システム障害のリスクがある・記録の共有に時間がかかる(回覧など)
・過去の記録を探すのが大変
・書き手によって文字の癖があり読みにくい
・紙の保管場所が必要近年は、業務効率化や情報共有の迅速性の観点から、介護ソフトやアプリを導入する事業所が増加傾向にあります。
- Q3. 研修などで介護記録を深く学ぶ方法はありますか?
-
A3. はい、事業所内外の研修や書籍で学ぶことができます。
よりスキルアップを目指したい方向けに、いくつかの学習方法を紹介します。【事業所内研修】(OJT)
まずは、所属する事業所の研修や、先輩職員からの指導(OJT)が基本となります。
事業所ごとのルールや書式を学び、不明な点は積極的に質問しましょう。【外部研修への参加】
自治体や地域の介護福祉士会、民間企業などが主催する「介護記録の書き方セミナー」などに参加するのも有効です。
他の事業所の職員と情報交換するよい機会にもなります。【書籍で学ぶ】
介護記録の書き方に関する書籍は数多く出版されています。
シーン別の文例集や、法的根拠に基づいた書き方を解説した本など、自分のレベルや目的に合った一冊を探しましょう。例えば、
などは、具体的な文例が豊富で、日々の業務の参考になります。
【まとめ】質の高い介護記録は、明日のケアを豊かにする第一歩

この記事では、介護記録の基本目的、5W1HやSOAP形式の書き方やシーン別例文、業務効率化とリスク管理について総合的に解説しました。
質の高い介護記録は、単なる日々の業務報告書ではありません。
自分がおこなったケアの価値を証明し、チーム全体のケアの質を高め、そして何より利用者の日々の暮らしを豊かにするための、極めて専門的な「技術」です。
この記事で得た知識を、明日からの実践に活かし、自分のケアをさらに豊かなものにしていきましょう。