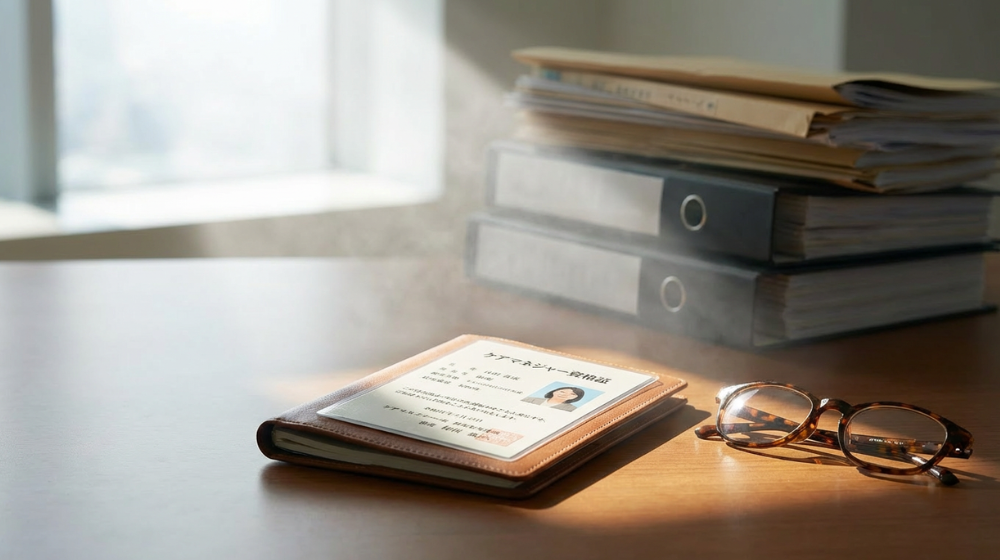記事公開日
【2025年8月最新】外国人による訪問介護が解禁!事業者向けに条件・課題・採用方法を徹底解説

深刻な人手不足に悩む訪問介護事業所にとって、2025年4月から解禁された「外国人介護人材による訪問介護」は大きな転機です。
すでに制度はスタートしており、条件を満たせば外国人ヘルパーを自宅介護の現場に迎えることが可能です。
この記事では、解禁の背景や制度の要点、メリット・課題、採用までの具体的な5ステップを徹底解説します。
採用のチャンスを逃さず、現場の負担を減らすための第一歩を踏み出しましょう。
訪問介護事業を継続・拡大したい方、人手不足に本気で悩む方はぜひ最後までご覧ください。
ついに「外国人 訪問介護」解禁!人手不足解消の切り札をどう活用しますか?

2025年4月、外国人介護人材による訪問介護がついに解禁されました。
厚生労働省は、特定技能および技能実習制度の枠組みを活用し、一定の条件を満たす外国人介護人材が利用者の自宅でサービスを提供できるよう制度を改正。
これは2024年3月11日の閣議決定を経て実施されたもので、慢性的な人手不足が深刻化する訪問介護分野における抜本的対策として位置づけられています。
これまで外国人による訪問介護は認められておらず、特養や有料老人ホームなど施設系サービスが中心でした。
しかし今回の規制緩和により、訪問介護事業所は若く意欲のある海外人材を直接現場に迎え入れられるようになりました。
なお、似た制度の「技能実習」と混同されがちですが、この記事で解説するのは就労を目的とした「特定技能」です。
技能実習は研修・習得が目的で就労期間や業務範囲が限られますが、特定技能は即戦力として長期的に活躍できる点が特徴です。
制度の違いを理解したうえで、今後の採用計画に活かしていきましょう。
特定技能に訪問介護が追加!制度変更のポイント
今回の制度改正の最大のポイントは、介護分野の特定技能1号の対象業務に「訪問介護」が正式に追加されたことです。
これにより、介護施設だけでなく、利用者の自宅に出向いてケアをおこなう訪問系サービスにも外国人介護人材が従事できるようになりました。
背景には、訪問介護特有の人手不足の深刻化があります。
施設勤務に比べて1対1のケアが求められ、移動時間や業務の個別性が高いため、採用難が続いていました。
厚生労働省はこうした現状を踏まえ、2025年3月の介護給付費分科会・介護保険部会で対象サービスの範囲や条件を説明し、制度の詳細を確定しました。
特定技能制度では、日本語能力試験(N4以上)や介護日本語評価試験、介護技能評価試験の合格が必要であり、基礎的な介護スキルと日本語でのコミュニケーション力を備えた人材が対象です。
この制度によって、利用者やその家族は、より安心して訪問介護サービスを受けられるようになると期待されています。
参考:厚生労働省「第245回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」「第118回社会保障審議会介護保険部会」「 介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
特定技能による訪問介護解禁のメリット

特定技能外国人の訪問介護への参入は、深刻な人材不足に悩む事業者にとって、多くのメリットをもたらす可能性を秘めています。
単なる労働力の確保に留まらない、事業の成長につながる2つの大きなメリットを解説します。
メリット1:若い人材の確保が期待できる
訪問介護は高齢化の進行により、深刻な「担い手不足」に直面しています。
特定技能制度を活用すれば、20〜30代を中心とした若い外国人介護人材を確保することが可能です。
若年層は体力や柔軟性に優れ、移動をともなう訪問介護の現場でも力を発揮できます。
また、ICTツールや新しい介護機器にも順応しやすい傾向があるため、業務効率化の推進にも貢献します。
さらに、キャリアの早い段階から受け入れることで、長期的な育成が可能です。
将来は事業所の中核を担う人材へと成長させることも期待できます。
メリット2:多様なニーズに対応できる
外国人介護人材の雇用は人手不足の解決だけでなく、事業所に新たな価値をもたらし、多様な利用者ニーズに応えられます。
例えば、外国語や異文化に精通した職員がいれば、国際結婚家庭や在日外国人高齢者とその家族へのサービス提供がよりスムーズになります。
母国語でのケアや宗教的習慣への配慮が可能になり、利用者と家族に大きな安心感を提供できるでしょう。
さらに、外国人介護職員の「なぜそうするの?」という素直な疑問が、当たり前になっていた業務プロセスを見直すきっかけになることもあります。
彼らの新鮮な視点は、職場の固定観念を打ち破り、組織全体に活力をもたらす力となります。
特定技能による訪問介護解禁の3つのデメリット

外国人介護人材の受け入れは多くのメリットをもたらす一方で、事前の対策がなければ思わぬ課題に直面する可能性もあります。
しかし、これらのデメリットは、適切な準備と理解によって乗り越えることが可能です。
ここでは、想定される3つのデメリットと、それぞれの具体的な対策について解説します。
デメリット1:日本語能力の個人差で意思疎通に問題が生じる
特定技能外国人は日本語能力試験N4以上などの基準を満たしていますが、会話のスピードや専門用語の理解度には個人差があります。
特に、利用者との細やかなコミュニケーションが求められる訪問介護の現場では、次のような課題が生じる可能性があります。
- 利用者の体調の微妙な変化や要望を正確に聞き取れない
- 方言や独特の言い回しが理解できず、会話が弾まない
- 緊急時に状況を的確に報告できない
【対策】
この課題を解決するには、利用者との会話を想定したロールプレイングや介護現場で頻出する単語・表現の学習機会を設けるなど、実践的な研修をおこなうことが効果的です。
また、指差しで意思疎通が図れる絵カードやふりがな付きマニュアル、ICTアプリなどを活用し、情報を視覚的に伝える工夫も有効です。
さらに、日本人職員が定期的に面談を実施し、コミュニケーション面での不安や悩みを早期に把握する体制を整えることで、現場での齟齬を減らせます。
デメリット2:文化的な違いで特定技能外国人や利用者・家族が違和感を覚える
食事や入浴、家族との関わり方など、生活習慣や文化は国によって大きく異なります。
こうした違いへの理解が不足していると、外国人介護職員と利用者・その家族の双方にとってストレスの原因となりかねません。
- 外国人介護職員側→日本の家庭における暗黙のルールが分からず、戸惑いや孤独を感じる。
- 利用者・家族側→職員の言動に違和感を覚え、不安や不信感を抱いてしまう。
【対策】
日本の生活文化や高齢者介護の価値観について具体的事例を交えて研修をおこない、外国人介護職員に事前知識を提供することが大切です。
加えて、利用者や家族には担当職員の出身国の文化や人柄に関して丁寧に説明し、理解を促します。
困ったときにすぐ相談できるメンター役の日本人職員を配置し、文化的背景も含めて支えられる環境を整えることも効果的です。
デメリット3:サポート体制の不備でトラブルが発生する
外国人介護人材が日本で安心して働き続けるためには、業務の指導だけでなく、生活面でのサポートが欠かせません。
特に、訪問介護は日中の大半を一人で業務にあたるため、孤立感を深めやすい傾向にあります。
サポート体制が不十分な場合、職員が抱える不安やストレスが増大し、サービスの質の低下や早期離職といった事態につながるリスクがあります。
【対策】
「採用して終わり」ではなく、受け入れ後の継続的な支援計画を立てましょう。
住居の確保や行政手続き、銀行口座の開設など生活基盤づくりを支援する担当者を配置し、定期的な面談や交流の場を通じて職員同士がつながれる環境をつくります。
また、利用者の体調急変など不測の事態に備え「誰に、どのように」連絡すればよいのかを明確化し、全員に周知することが重要です。
【5ステップで実践】外国人を訪問介護で雇用するための全手順

外国人介護人材の雇用を成功させるためには、計画的かつ着実な準備が必要です。
ここでは、採用計画から就業後のフォローまで、具体的な5つのステップに分けて解説します。
- ステップ1:受け入れ要件の最終確認をする【自社は対象か?】
- ステップ2:求人・採用ルートの選定をする【最適な人材はどこに?】
- ステップ3:各種申請・手続きをする【専門家の活用も視野に?】
- ステップ4:受け入れ体制を構築する【定着してもらうには?】
- ステップ5:雇用契約と就業開始後のサポート体制を用意する【採用して終わりじゃない】
それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1:受け入れ要件の最終確認をする【自社は対象か?】
まずは「自社が受け入れ可能か」をチェックします。
ポイントは表のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象サービスの確認 | 訪問介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/総合事業(第一号訪問)に加え、訪問入浴介護も従事可能(入浴は職場内研修の実施が前提) |
| 人材側の基礎要件 | 原則:介護職員初任者研修等の修了+介護事業所での実務経験1年以上の外国人(特定技能・技能実習) |
| 例外運用 | 実務1年未満でも、N2相当など高い日本語力+利用者ごとの長期同行(回数・期間の下限あり)等の追加条件を満たす場合に限り可 |
| 受け入れ事業所の 「5つの遵守事項」 |
① 研修(訪問系の基本・生活支援技術・緊急時対応) ② 同行訪問(OJT)の実施 ③ 丁寧な説明とキャリアアップ計画の共同策定 ④ ハラスメント対策(窓口・ルール整備) ⑤ ICT活用(緊急時連絡・記録共有体制) |
| 利用者・家族への 書面説明と署名 |
訪問予定・実務経験・ICT機器使用の可能性・連絡先を書面で説明し、署名を取得 |
| 報酬の考え方 | 在留資格の趣旨上、日本人と同等程度の職務に対して同等額以上の報酬が必要 |
上記の基本要件・ポイントに加え、特に注意すべき点をいくつか補足します。(詳細はステップ3以降で具体的に解説します)
例えば、例外的に実務経験1年未満の人材を受け入れることも可能ですが、その場合は利用者ごとに長期間の同行訪問(OJT)が義務付けられるなど、事業所の指導・育成負担は格段に重くなります。
なかでも、利用者の居宅という閉鎖された空間で1対1のサービスを提供する特性上、ハラスメント対策は極めて重要です。
また、一人で現場に向かうことが多い訪問介護員の精神的な不安を解消するために、今やICTの活用は欠かせません。
まずは、上記の要件をすべて満たせるかどうか、自事業所の現状を客観的に評価することが、外国人介護人材の受け入れにおける最初のステップです。
受け入れの見通しが立ったら、次のステップとして、具体的にどのような方法で人材を探すのかを検討していきましょう。
参考:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」「 外国人介護人材が訪問系サービスに従事できるようになりました」「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)」
ステップ2:求人・採用ルートの選定をする【最適な人材はどこに?】
採用効率を上げるには、「国内の特定技能保有者」と「海外からの採用」を並行検討するのが定石です。
国内では、学習・就労中の外国人(特定技能・元技能実習など)からの転職母集団を狙うと、入職までのリードタイムを短縮できます。
海外採用では送出機関・学校・紹介会社を活用し、事前学習(初任者相当の理解や介護日本語)を条件化するとミスマッチを抑制できます。
利用可能な紹介サービス・求人媒体は次の表をご覧ください。
【公的ルート】
| 窓口/サービス | 主な役割・特徴 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| ハローワーク インターネットサービス(ハローワーク) | 医療・介護求人の掲載・応募受付 ※地域の求職者母集団に強い |
無料掲載/地域採用に最適。訪問系のOJTやICT体制を求人票に明記 |
| JICWELS(特定技能関連) | 特定技能の相談・情報提供、巡回訪問の案内など | 制度疑問の解消に最適。適合確認や運用の最新情報を確認 |
| JICWELS(EPA介護福祉士候補者) | EPAルートの受け入れ・マッチング募集(年度運用) | 施設中心だがトレンド把握に有用。情報収集の窓口として活用 |
| 登録支援機関(RSO)検索(出入国在留管理庁/法務省) | 支援委託先を検索・比較(対応地域・言語・実績等) | 候補機関の支援内容・体制・実績を確認して委託先選定 |
| 送り出し機関一覧(OTIT) | 技能実習ルートの海外窓口を国別に把握 | 国・機関ごとの信頼性と実績を確認して連携先を検討 |
【民間ルート】
| ルート | 主な役割・特徴 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 有料職業紹介事業者(介護特化/外国人採用対応) | 特定技能・元技能実習・留学生から転職候補者を提案 | 職業紹介許可番号・特定技能支援実績・定着支援の中身を要確認 |
| 介護専門の求人サイト/転職媒体 | 国内在住の特定技能人材へ広くリーチ | 求人票に訪問系の研修・同行OJT・ハラスメント対策・ICT支援を具体的に記載しミスマッチ抑制 |
| 日本語学校・介護研修機関との連携 | 初任者研修や介護日本語を履修済みの候補者を紹介 | 事前学習要件(初任者相当・介護日本語)を合意し、入職後研修と接続 |
民間ルートを使いどころ別に整理しました。
| カテゴリ | 民間ルート(サービス名) | 何ができるか | 補足 |
|---|---|---|---|
| 有料職業紹介/求人媒体(介護特化) | (旧:カイゴジョブ) |
介護分野の求人掲載・応募受付。母集団が大きい | 旧カイゴジョブの大型サイト。地域求人に強い |
| <レバウェル介護 (旧:きらケア) |
転職支援(紹介)/求人掲載 | 面談~内定まで伴走するエージェント型 | |
| マイナビ介護職 | 転職支援(紹介)/求人掲載 | ブランド認知が高く、全国網羅 | |
| 介護ワーカー | 転職支援(紹介) | 介護専門の紹介会社。支店網が広い | |
| ツクイスタッフ(かいごGarden) | 転職支援(紹介・派遣)/求人掲載 | 現場ノウハウに基づくマッチング。 | |
| 外国人向け求人サイト | WeXpats Jobs | 日本在住の外国人向け求人。日本語レベルで検索可 | 特定技能・介護の求人も多い |
| 外国人向け総合求人 | 英語UI。介護求人も散発的に掲載 | ||
| 特定技能に強い紹介・登録支援機関 | スタッフプラス | 特定技能(介護)人材の紹介/登録支援 | 海外教育機関と連携、支援一体型 |
| マイナビグローバル | 特定技能(介護)人材の紹介/登録支援 | 5,300名規模の支援実績を公表。資料提供もある | |
| 研修機関/学校との連携(母集団形成) | ニチイ学館 (初任者研修) |
初任者研修の受講者ネットワークと連携 | 研修やカリキュラム情報の確認・協業に。 |
| 三幸福祉カレッジ | 外国人向け実務者研修・専用クラス | ふりがな教材・動画等で外国人受講に配慮 |
公的ルートは、制度面の確認とコンプライアンスの担保に有効です。
ハローワークで地域母集団に広く告知しつつ、国際厚生事業団(JICWELS)で最新の運用や巡回対応を把握。
委託が必要な場合は、法務省の「登録支援機関(RSO)検索」で支援内容・言語・実績を比較し、OTITの送り出し機関一覧で海外側の信頼性も確認します。
一方、民間ルートはスピードと到達範囲が強みです。
介護特化の紹介会社・求人媒体で国内在住の特定技能人材に素早くアプローチし、日本語学校や研修機関と連携して「初任者相当・介護日本語」などの事前学習条件を整えるとミスマッチが減ります。
求人票には、
- 研修
- 同行OJT
- ハラスメント対策
- ICT支援
を具体的に記載し、「安心して働ける現場」を明確に打ち出しましょう。
採用ルートの基盤が整ったら、委託先の実績確認を完了させ、次は在留資格や適合確認などの手続き段階へ進みます。
参考:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」「 令和7年度新規学校卒業予定者の求人・募集の手引き」
ステップ3:各種申請・手続きをする【専門家の活用も視野に?】
採用する外国人介護人材が決まったら、在留資格の申請と訪問系サービス従事の適合確認申請という、2つの公的手続きを並行して進めます。
訪問介護で従事してもらうには、厚生労働省が定める条件のもと、公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)への適合確認申請(従事前)が必須です。
適合確認書の交付後は、巡回訪問への対応や、策定したキャリアアップ計画の定期的な更新・提出が求められます。
在留資格については、採用ルートによって手続きが異なります。
- 海外在住者採用:在留資格認定証明書(COE)交付申請 → 交付後に査証申請 → 入国。
- 国内在住者採用:在留資格変更許可申請 → 在留カード更新 → 就労開始。
実務では、いずれの手続きも不備が発生すると審査遅延の原因となります。
そのため、申請書類の作成や証憑整備に不安がある場合は、特定技能(介護)の実績を持つ行政書士や登録支援機関の活用が有効です。
適合確認および在留資格の申請準備では、ステップ4のなかで解説するマニュアルや、ステップ5の契約書に反映しておくことが重要です。

参考:厚生労働省「 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」「外国人介護人材が訪問系サービスに従事できるようになりました」「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)」
手続きは、適合確認(1.5~2ヵ月程度)と在留資格審査(1~3ヵ月程度)を逆算し、並行管理することがポイントです。
採用予定日に間に合うよう、早期着手を心がけましょう。
ステップ3はここまでです。
手続きの見通しが立ったら、次は受け入れ体制を現場で効果的に機能させる段階に進みます。
ステップ4:受け入れ体制を構築する【定着してもらうには?】
採用が決まったら、外国人介護人材がスムーズに日本での仕事と生活をスタートできるための受け入れ体制を構築します。
法律で定められた支援計画を確実に実行することはもちろん、職員が安心して長く働ける環境を整えることが、早期離職を防ぎ、人材定着を成功させます。
国が定める遵守事項(=受け入れ体制の柱)は次の5つです。
① 訪問介護の業務の基本事項等に関する研修実施
② サービス提供責任者等による一定期間の同行等のOJTの実施
③ 外国人介護人材への丁寧な説明、外国人介護人材との共同でのキャリアアップ計画の作成
④ マニュアルの作成や相談窓口の設置等によるハラスメント対策
⑤ 不測の事態に備えたICT活用等の環境整備引用:厚生労働省「外国人介護人材が訪問系サービスに従事できるようになりました」
上記5つの遵守事項をより分かりやすく解説するため、7つの観点に分けてまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。
-
実践的な研修プログラム(Off-JT)
厚生労働省は、訪問系に従事する外国人介護人材に対して、以下を含む研修の実施を求めています。- 訪問系サービスの基本事項と生活支援技術(居宅で実施する行為の基礎)
- 利用者・家族・近隣とのコミュニケーション(傾聴・受容・共感などのスキル)
- 日本の生活様式や家庭内マナーの理解(靴・持ち物の扱い等の生活慣習)
- 緊急時対応(連絡先・連絡方法の事前確認を含む、想定訓練)
これらは受け入れ事業所が計画化し、巡回訪問等実施機関から求められた際に提示できる体制が必要になります。
-
同行訪問によるOJT(段階的独り立ち)
外国人介護人材が訪問系サービスをスムーズに提供できるよう、受け入れ事業所には「同行訪問によるOJT」という段階的な指導体制の実施が義務付けられています。- 受け入れ事業所は、外国人介護人材が一人で適切にサービス提供できるまで、サービス提供責任者等が一定期間「同行訪問」をおこなう
- 指導は段階的に、見学→部分実施→主担当+同行者が確認、のステップでおこなうことが想定される
- 例外として、実務1年未満の受け入れでは、利用者ごとに必須の同行期間(週1=6ヵ月、週2=3ヵ月、週3回以上=2ヵ月。週1は家族同意+見守りカメラ等のICT併用で3ヵ月に短縮可)を満たす必要がある
- あわせて、事業所に戻ってからの面談・振り返りや日本語学習支援の機会を多めに設ける等、状況に応じた配慮が求められる
このように、同行訪問OJTは外国人介護人材の成長と、利用者・家族の安心感醸成の両面で極めて重要な役割を担っています。
-
生活・就労の支援体制(安心して働ける基盤)
外国人介護人材を受け入れる事業所は、彼らが安全かつ安心して業務を継続できるよう、適切な生活・就労支援体制の整備が求められています。- 訪問系は1対1の提供で孤立しやすいため、相談できる体制と定期面談を設けることが推奨
- 国は巡回訪問体制と第三者相談窓口(多言語)を整備しており、周知と活用が想定されている
- キャリアアップ(介護福祉士取得を含む)や日本語学習の継続支援、基金事業等の活用が案内されている
これらの取り組みは、外国人介護人材がストレスなく長く働き続けられる環境づくりのために欠かせません。
-
ハラスメント対策(必須の遵守事項)
外国人介護人材の権利保護のため、事業所は包括的なハラスメント対策が「必須の遵守事項」となっています。- 受け入れ事業所は、マニュアル整備・役割明確化・対処ルール・相談窓口の設置と周知をおこなう
- 1対1の特性上、未然防止と迅速なエスカレーションが重要で、国作成のマニュアル・研修手引き・事例集の活用が推奨
安心して働ける環境を構築することが、利用者と介護人材双方の信頼維持につながります。
-
ICT活用を含む環境整備(安全・連絡・記録の基盤)
次の環境整備に関する事項は「いずれも実施が必要」と明示されています。- 緊急時の連絡先・対応フローのマニュアル化
- 緊急時を想定した研修の実施
- 駆け付け体制の確保
- 記録・申し送りの情報共有仕組み(記録作成の負担軽減や簡略化を含む)
具体的なICT例として、コミュニケーションアプリ(翻訳含む)、見守りカメラやセンサー、音声入力・多言語翻訳に対応した記録ソフトや学習教材などが示されています。
-
利用者・家族との合意形成(書面説明と署名)
訪問系サービスに外国人介護人材を受け入れる際には、利用者・家族と十分な合意形成を図りましょう。- 外国人介護人材が訪問する可能性、実務経験(期間等)、ICT機器使用の有無、連絡先を「書面で説明し署名取得」する(様式は別添)
- 訪問先の選定は、利用者の状態像(健康・ADL・認知症自立度・居住環境)や利用者・家族の意向、人材のコミュニケーション力・技術などを踏まえ、総合判断して記録に残す
このようなアクションは、利用者・家族、そして外国人介護人材双方の納得と安心につながります。
-
キャリアアップ計画(共同策定と定期更新)
外国人介護人材の成長と長期活躍のため、事業所には「本人と共同でキャリアアップ計画を策定・定期的に更新」の運用が求められます。- 外国人介護人材の意向確認をおこない、目指すべき姿・技能、資格取得等を含めたキャリアパスを前提に、本人と共同で「キャリアアップ計画」を策定・共有する
- 計画は定期的に更新し、巡回訪問等実施機関に提出する
成長に向けた支援は人材定着だけでなく、サービス品質確保にも直結し、外国人介護人材を受け入れる事業所の責務として重要視されています。
参考:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)」
以上、7つの観点は単なる規則ではなく、外国人介護人材と事業所、そして何より利用者との信頼関係を築くための基盤です。
着実に実施することで、外国人による訪問介護が安全かつ効果的におこなわれ、人手不足の解消と同時にサービスの質の向上も実現できるでしょう。
ステップ5:雇用契約と就業開始後のサポート体制を用意する【採用して終わりじゃない】
最後のステップは、適切な雇用契約の締結と、就業開始後の継続的なサポート体制の準備です。
採用はゴールではなく、外国人介護人材が事業所の貴重な一員として、共に成長していくためのスタート地点と捉えましょう。
【雇用契約締結時の法的注意点】
外国人介護人材と雇用契約を結ぶ際は、文化や言語の違いによるトラブルを未然に防止するため、特に以下の点に注意し、法律を遵守する必要があります。
-
労働条件の明確な説明と書面交付
賃金や労働時間、業務内容といった重要な労働条件について、本人が十分に理解できる言語(母国語)を併記した雇用契約書や労働条件通知書を作成し、交付することが法律で義務付けられています。
口頭での説明だけでなく、必ず書面で明確に示すことが重要です。 -
日本人と同等以上の報酬の保証
外国人であることを理由に、不当に低い賃金で雇用することは決して許されません。
同じ業務に従事する日本人職員と同等以上の報酬水準に設定することが、特定技能制度の要件としても定められています。 -
日本の労働法規の遵守
労働時間、休日、有給休暇、社会保険への加入など、すべて日本の労働関連法規に則る必要があります。
これは、日本人と外国人という区別なく、すべての職員に適用される大原則です。
【就業開始後の継続的なサポート体制】
「採用して終わり」ではなく、共に働く大切なパートナーとして迎え入れる姿勢が、外国人介護人材の定着を左右します。
-
公的機関への対応と定期的な面談の実施
事業者は、国際厚生事業団(JICWELS)による定期的な巡回訪問を受け入れ、状況を報告する義務があります。
それと連動し、日頃からサービス提供責任者などが定期的に面談(1on1など)をおこない、業務の進捗やキャリアアップの意向、生活上の不安などをヒアリングする機会を設けましょう。
問題の早期発見と解消につながります。 -
職場全体でのコミュニケーション促進
孤立は、早期離職の最大の原因です。
日本人職員との交流会を企画したり、業務の情報共有を密にしたりと、職場全体でコミュニケーションを取り、チームの一員として迎え入れる環境をつくることが大切です。 -
トラブル発生時の迅速な対応
文化や習慣の違いから、利用者やその家族との間で予期せぬトラブルが発生する可能性もあります。
問題が起きた際に、事業者として責任を持って迅速かつ適切に対応できる体制を事前に整え、外国人介護職員が一人で抱え込まないようにサポートしましょう。
外国人介護人材を単なる「労働力」としてではなく、事業所の未来を共につくる「パートナー」として尊重し、継続的な支援をおこなうこと。
それが、外国人介護人材の雇用を成功させる、何より重要な考え方です。
【FAQ】外国人 訪問介護に関するよくある質問

外国人による訪問介護に関するよくある質問を、事業所の経営者向けにQ&A形式でまとめました。
「実際に受け入れ可能か」という基本的な質問から外国人介護人材の現状まで、簡潔に回答します。
Q1. うちの事業所でも、本当に外国人を訪問介護で受け入れられますか?
A1. はい、2025年4月から制度が開始されており、要件を満たせばどの事業所でも受け入れは可能です。
ただし、誰でも無条件に雇用できるわけではありません。
これまで解説してきた通り、受け入れを成功させるためには、以下の2つの側面から国が定める条件をすべてクリアする必要があります。
【外国人介護人材側の条件】
- 原則1年以上の実務経験
- 介護職員初任者研修の修了
- 特定技能として必要な試験の合格 など
【事業所側の条件】
- 利用者・家族への事前説明と同意
- 5つの遵守事項(研修/OJT/キャリアアップ計画/ハラスメント対策/ICT環境整備)を履行できる体制
- 国際厚生事業団(JICWELS)への適合確認申請 など
これらの準備と体制構築をしっかりとおこなえるかが、受け入れの可否を判断するポイントになります。
Q2. 全体として、外国人介護人材の受け入れは進んでいますか?
A2. はい、受け入れは拡大基調です。
特定技能「介護」の在留者は2019年の開始以降増加を続け、2024年12月末に約4.4万人で過去最多となりました。
2025年の制度改正で訪問系への従事が広がり、今後は在宅分野でも活躍の場が拡大すると見込まれます。
参考:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」
【まとめ】変化をチャンスに!外国人介護人材と共に訪問介護の新たなステージへ

2025年4月から解禁された、外国人介護人材による訪問介護。
この記事では、制度の概要から具体的な受け入れ手順、そして成功のためのポイントまでを網羅的に解説してきました。
外国人介護人材の受け入れは、単なる人手不足の解消策ではありません。
それは、多様な視点と活気を事業所にもたらし、変化する介護ニーズに対応するための未来への重要な「投資」です。
彼らと共に働くことで、組織は新たな価値を生み出し、より強く成長できるしょう。
しかし、制度の理解から煩雑な申請手続き、受け入れ後の支援まで、そのすべてを経営者や管理者が一人で抱え込む必要はありません。
何から手をつければよいか迷ったら、登録支援機関や行政書士といった専門家へ相談しましょう。
この歴史的な「変化」を「チャンス」と捉え、新たな仲間と共に、訪問介護事業の新しいステージへと踏み出しましょう。
外国人介護職員も使いやすい業務支援アプリ「ファーストケア・アサインPro/アサインモバイル」

外国人介護人材の受け入れを成功させるポイントは、丁寧な初期教育と、日々の業務における継続的なサポート体制にあります。
しかし、現場での指示出しやサービス記録が複雑では、言語の壁もある外国人介護職員にとって大きな心理的負担となり、サービスの質の低下や早期離職の原因にもなりかねません。
そのような課題を解決するのが、訪問介護の指示・実施業務管理に特化したアプリ「ファーストケア・アサインPro/アサインモバイル」です。
サービス提供責任者は「ファーストケア・アサインPro」で、利用者一人ひとりに対するケアの指示を写真や申し送り事項と共に明確に作成。
現場の職員は「ファーストケア・アサインモバイル」でその指示内容を確認し、あとは実施した項目にチェックを入れたり、記録するだけの簡単操作です。
複雑な文章入力は必要なく、直感的な操作で業務が完結するため、日本語での記録に不慣れな外国人介護職員の方でも迷うことなく使いこなせます。
言語や経験の違いを超えて、すべての職員が安心して質の高いサービスを提供できる環境を実現しましょう。
まずは無料の資料請求で、「アサインPro/アサインモバイル」が現場の負担をどう軽減できるのか、その機能詳細をご確認ください。