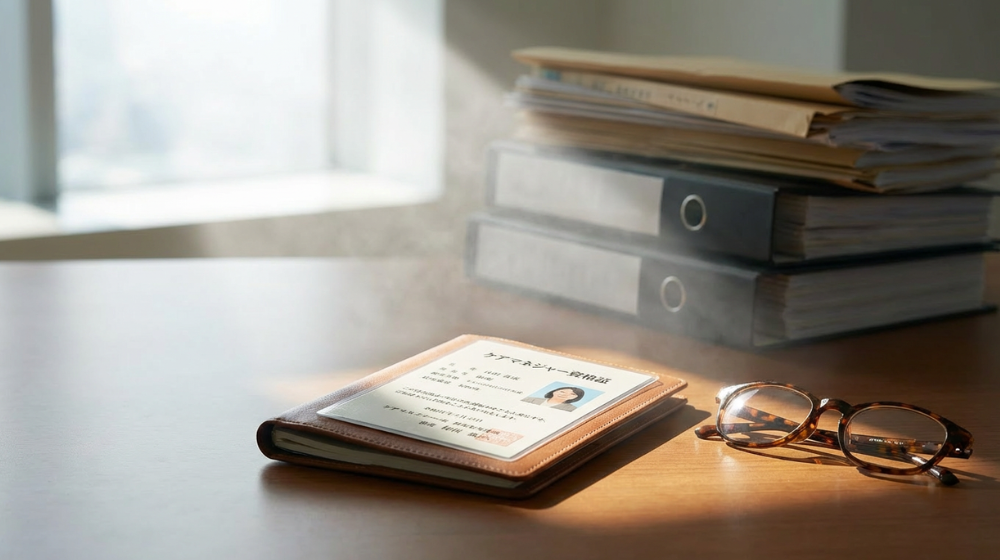記事公開日
介護ソフトの乗り換えで失敗しない!データ移行・タイミング・費用・選び方を徹底解説

介護ソフトの乗り換えは、正しい手順とポイントをおさえれば失敗せずに成功できます。
多くの事業所が情報収集の不足や、データ移行の計画の甘さが原因でつまずきがちです。
しかし、課題を明確にすることで、これらの問題は十分に解決可能です。
この記事では、乗り換えに最適なタイミングから、後悔しないための具体的な3ステップ、そして最も不安なデータ移行の注意点まで網羅的に解説します。
自分の事業所に最適な介護ソフトを選び、自信を持って乗り換えを進めるための全知識を手に入れましょう。
【今回の記事が役立つ方々】
- 現在の介護ソフトに不満があり、日々の業務を効率化したい方
- 乗り換えの具体的な手順や、失敗しないための注意点を知りたい方
- コストを抑えつつ、自分の事業所に最適な介護ソフトを選びたい方
ぜひ最後までご覧ください。
『その悩み、プロに相談すれば「やることリスト」に変わります』
もし、この記事を読み進める前に「うちの事業所特有の課題はどうすれば……」という個別の不安を今すぐ解消したいとお考えなら、専門家への相談が一番の近道です。
乗り換えに関するどのような些細なお悩みでも、まずは弊社へお気軽にお聞かせください。
お問い合わせはこちら
介護ソフトの乗り換えを事業所が検討する5つの理由

「うちだけだろうか…」と感じるその悩みは、実は他の事業所も共通して抱える問題なのかもしれません。
もし、次にある5つのいずれかに当てはまるなら、それは乗り換えを検討する重要なサインです。
【理由1】記録や請求作業が手間取る
「毎日、記録の入力だけで1時間以上かかっている」「月末の請求作業で、必ず誰かが残業している」といった状況は当たり前ではありません。入力項目が多すぎる、動作が遅い、帳票作成が複雑など、職員の貴重な時間を奪う介護ソフトは業務効率化の最大の障壁です。
【理由2】ソフトの料金が高すぎる
「初期費用は安かったのに、月額料金やオプション費用がかさんでいる」「法改正のたびに、高額なバージョンアップ費用を請求される」など、コストに関する不満は経営に直結します。見えない費用が発生し、トータルコストが経営を圧迫しているなら、料金体系の見直しが必要です。
【理由3】サポートが不十分
「操作で困った時に電話しても、なかなかつながらない」「質問への回答が遅く、業務が止まってしまう」「担当者が介護現場の状況を理解してくれない」といった経験はありませんか?いざという時に頼れないサポート体制は、現場の職員にとって大きなストレスとなり、業務停滞のリスクにもなります。
【理由4】法改正への対応が遅い
頻繁におこなわれる介護報酬改定や制度変更。これらへの対応が遅かったり、追加費用を求められたりする介護ソフトでは、将来にわたって安心して事業を継続できません。迅速かつ正確な法改正への対応は、介護ソフト選びの重要な要件です。
【理由5】職員同士の情報共有がうまくいかない
「事務所に戻らないと、他の職員の記録を確認できない」「口頭での申し送りが中心で、伝達漏れが心配」といった課題は危険です。リアルタイムな情報共有ができないと、ケアの質にばらつきが生じるだけでなく、ヒヤリハットや事故につながる危険性も高まります。職員間の円滑な連携は、質の高い介護サービスの提供に不可欠です。
参考:厚生労働省「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」
これらの課題は、日々の業務に潜む「見えないコスト」です。
1つでも心当たりがあれば、前向きに介護ソフトの乗り換えを検討しましょう。
介護ソフトの乗り換えに最適なタイミングはいつ?

介護ソフトの乗り換えは、思い立ったらいつでもできるわけではありません。
業務への影響を最小限におさえ、スムーズに移行するためには「タイミング」が非常に重要です。
ここでは、乗り換えに最適な時期と、逆に避けたい時期を具体的に紹介します。
- 【最適】国保連への請求業務(毎月1日~10日)が終わった直後
- 【最適】現在の介護ソフトのリース契約や年間契約の更新時期
- 【注意】事業所の繁忙期や介護報酬改定の直前直後
それぞれの理由を解説します。
【最適】国保連への請求業務(毎月1日~10日)が終わった直後
介護事業所の業務サイクルのなかで、最も乗り換えに適しているのが、毎月10日の国保連への請求業務が終わった直後です。
月で最も重要かつ複雑な請求業務が完了しているため、現場の職員も経営者も、精神的な余裕を持って新しい介護ソフトへの移行作業に着手できます。
また、月次の請求データが確定したあとの移行は、請求漏れや二重請求などの重大なミスを防ぎやすく、データ管理の区切りとしても最適です。
多くの事業所が「11日以降」を乗り換えのタイミングに設定しています。
【最適】現在の介護ソフトのリース契約や年間契約の更新時期
経営的な視点では、現在使っている介護ソフトの契約更新時期も、絶好のタイミングです。
特にリース契約の場合、契約期間の途中で解約すると高額な違約金が発生する可能性があります。
契約が満了するタイミングで解約・乗り換えをおこなえば、無駄なコストの発生を防げます。
契約満了の3~6ヵ月前から乗り換えの検討をはじめ、情報収集とソフト選定を計画的に進めていきましょう。
【注意】事業所の繁忙期や介護報酬改定の直前直後
一方で、乗り換えを避けるべきタイミングも存在します。
それは、年末年始や年度末といった事業所の繁忙期、そして最も注意すべきなのが「介護報酬改定」の直前直後です。
これらの時期は、職員が通常業務や新しい制度への対応で手一杯です。
そこに、介護ソフトの変更という大きな負荷をかけると、現場が混乱し、かえって業務効率が悪化するリスクがあります。
また、報酬改定直後は、事業者も介護ソフトベンダーも、新しい算定要件への対応で非常に慌ただしくなります。
法改正への対応が落ち着き、安定してから検討するのが賢明です。
介護ソフトの乗り換えを成功させる3ステップ

「介護ソフトを乗り換えたいが、何から手をつければいいのか、まったくわからない…」
その不安を解消するため、介護ソフトの乗り換えを成功に導く具体的な手順を、3つのシンプルなステップに分けて解説します。
下記にあるステップのとおりに進めれば、担当者一人に負担が偏ることなく、事業所全体で迷わずスムーズな移行が可能です。
- ステップ①:【準備】現状課題を洗い出し、乗り換えの目的を明確にする
- ステップ②:【選定】自分の事業所に合うソフトを比較検討し、決定する
- ステップ③:【実行】データ移行と導入・教育の計画を立てる
詳しくみていきましょう。
ステップ①:【準備】現状課題の洗い出し、目的を明確にする
介護ソフトの乗り換えは、準備の段階で成功が左右されるといっても過言ではありません。
「なぜ乗り換えるのか」という目的が曖昧なままでは、最適な介護ソフト選びは不可能です。
まずは足元を固めることからはじめましょう。
【現在のソフトの不満点をリストアップする】
経営者や現場責任者だけでなく、実際にソフトを毎日利用する職員の声を集めることが重要です。
「〇〇の入力に時間がかかる」
「この機能が使いにくい」
といった具体的な不満点を、立場に関わらず、すべてリストアップします。これにより「機能面」「コスト面」「操作性」「サポート面」の4つの観点で課題が整理され、問題点が明確になります。この作業が、次の「新しい介護ソフトに求めること」を具体化させるベースとなるでしょう。
【新しい介護ソフトに求める機能や条件に優先順位をつける】
リストアップした課題をもとに、新しい介護ソフトに求める要件を整理します。この時「譲れない条件(Must)」と「あれば嬉しい条件(Want)」に分けて優先順位をつけるのがポイントです。
例えば「LIFEに対応していること」や「データ移行のサポートが手厚いこと」は多くの事業所にとって「譲れない条件」でしょう。一方で「会計ソフトとの連携」は「あれば嬉しい条件」かもしれません。軸を明確にすることで、介護ソフト選定の際に判断に迷うことがなくなります。
【乗り換えの目的を全職員で共有する】
なぜ介護ソフトを乗り換えるのか、目的を必ず全職員で共有しましょう。「経営層が勝手に決めた」という印象を与えると、導入後に職員の協力が得られず、新しい介護ソフトが定着しない原因になります。
「職員の残業時間を減らし、本来のケアに集中できる環境をつくるため」
「より質の高い介護サービスを利用者に提供するため」
といった前向きな目的を共有することで、職員も当事者意識を持って協力してくれるでしょう。
ステップ②:【選定】自施設に合うソフトを比較検討し、決定する
準備が整ったら、次はいよいよ最も重要な介護ソフト選定のステップです。 後悔しないためには、自社で定めた基準をもとに、客観的な視点で候補を比較検討する必要があります。
ここでは、介護ソフトの本質を見極めるための5つのポイントと、具体的な比較方法を解説します。
後悔しないための5つのポイント
介護ソフトの乗り換えを成功させるために、サポート体制、操作性、コストなど下記にある5つの基準で評価しましょう。
1. サポート体制の手厚さ | 困った時に本当に頼れるか?
トラブル発生時や操作に迷った際、迅速かつ的確に対応してくれるヘルプデスクがあるかは極めて重要です。特に介護保険制度に詳しい専門スタッフがいると安心です。
2. データ移行の実績と柔軟性 | 最も不安な作業を安心して任せられるか?
乗り換えの最大の壁であるデータ移行。利用者情報や過去の請求データを安全に移行できるか、他社ソフトからの移行実績が豊富かを確認しましょう。
3. 現場での操作のわかりやすさ | パソコンが苦手な職員でも直感的に使えるか?
どんなに高機能でも、現場で使われなければ意味がありません。パソコンやタブレット操作が苦手な職員でも、直感的に使えるシンプルな操作性が確保されているかを見極めましょう。
4. 機能の過不足 | 業務に合う機能が揃っているか?
自分の事業所の業務フローに必要な機能が過不足なく揃っているかを確認します。多機能すぎても使いこなせず、コストが無駄になる可能性があります。
5. トータルコスト | 月額料金だけでなく、長期的な費用対効果は高いか?
初期費用や月額料金だけでなく、法改正対応やサポートにかかる追加費用も含めたトータルコストで比較し、費用対効果を判断することが大切です。
参考:厚生労働省「介護ソフトを選定・導入する際のポイント集」
これらのポイントをもとに、介護ソフトのタイプを比較してみましょう。
【比較表】介護ソフトのタイプ別比較
| ポイント | ファーストケア (サポート・実績重視) |
A社 (帳票充実) |
B社 (経営支援・多機能) |
C社 (医療連携特化) |
D社 (低価格・シンプル) |
|---|---|---|---|---|---|
| ①サポート体制 | ◎ 電話・遠隔・訪問まで手厚い |
〇 電話・メールが中心 |
〇 電話・メールが中心 |
〇 専門知識を持つ担当者が対応 |
△ オンラインサポートが中心 |
| ②データ移行 | ◎ 他社からの移行実績が豊富 |
〇 同社製品からの移行に強い |
〇 移行可能だが要件確認が必要 |
〇 専門データ移行に知見 |
△ 利用者自身での作業が多い |
| ③操作性 | ◎ シンプルで直感的 |
〇 慣れが必要な場合も |
△ 多機能な分、画面が複雑 |
〇 専門的だが整理されている |
◎ 機能が少なくシンプル |
| ④機能の範囲 | 〇 記録・請求などでコスト業務に特化 |
◎ 帳票種類が豊富、法人管理に強い |
◎ 採用・営業支援など周辺機能も網羅 |
◎ 医療・リハビリ情報との連携に強み |
△ 基本的な機能に限定 |
| ⑤トータルコスト | 〇 手厚いサポート込みで高コスパ |
△ 初期費用が高額になる傾向 |
△ 月額は高め、多機能分の費用 |
△ 専門性が高く、比較的高額 |
◎ 業界最安クラスの価格帯 |
| おすすめの事業所 | サポートを重視し、安心して乗り換えしたいすべての事業所 | 複数の介護サービスを運営する大規模法人 | 経営全般を効率化したい中~大規模 | 訪問看護などの医療系サービスを提供する事業所 | コスト最優先の小規模事業所 |
このように、各ソフトには一長一短があります。
多機能な介護ソフトが、必ずしも自分の事業所に合うとは限りません。
大切なのは、現在の課題を解決してくれる機能が過不足なく揃っており、職員全員がストレスなく使え、いざという時に頼れるサポートがあるかを見極めることです。
『わからないを残さない。それが本当のサポート。』
「ファーストケア」は、介護現場の声をもとに開発された、シンプルで使いやすい介護ソフトです。
導入時の不安を軽減する丁寧なサポート体制と、スムーズなデータ移行支援も可能で「ITが苦手な職員でもすぐに使えた」との声も多く寄せられています。
これまでに全国4,000以上の事業所で導入されており、豊富な実績とノウハウをもとに、現場に寄り添った対応を実現しています。
経験豊富な専門スタッフが相談から運用開始までサポートするため、業務への影響を最小限に抑えつつ、安心して切り替えられます。
「わからない」を残さず、確実な乗り換えを実現したい方は、ぜひご相談ください。
デモや無料トライアルで最終確認
資料や比較表だけで判断せず、必ず検討中の介護ソフトのデモや無料トライアルを体験してください。
実際に現場の職員が操作してみて「使いやすい」と実感できることが、導入後のスムーズな定着につながります。
デモを依頼する際は、自分の事業所の業務フローに沿った操作を試させてもらえるか確認しましょう。
ステップ③:【実行】データ移行と導入・教育の計画を立てる
導入するソフトが決まったら、いよいよ実行のステップです。
実際に現場のこの段階で焦ってしまうと、
「データが正しく移行できていない」
「職員が使いこなせない」
といったトラブルを引き起こす原因となります。
これらの問題を防ぐために、下記2点が重要です。
- データ移行の計画・準備
- 導入・教育の計画
具体的に、どのように計画を立てればよいのか、みていきましょう。
データ移行の計画・準備
乗り換えにおける最大の山場が、データ移行の計画や準備です。
ここで入念な計画を立てることが、移行作業をスムーズにできるかを決定づけます。
ベンダーと密に連携し、安全で確実な移行手順を確認しましょう。
【移行できるデータの範囲と移行できないデータを確認する】
利用者情報、ケアプラン、過去の請求履歴など、どのデータがどこまで移行できるのかを詳細に確認します。移行できないデータは、どう扱うのか(手入力する、紙で保管するなど)も決めておきましょう。
【データ移行の手順・スケジュール・費用をベンダーに聞く】
「いつ、誰が、何をするのか」という具体的なスケジュールと役割分担を明確にします。データ移行にかかる費用も、この時点で最終確認しておきましょう。
【万が一に備え、全データのバックアップを取る】
移行作業を開始する前には、既存ソフトの全データを複数の媒体(外付けHDDやクラウドなど)にバックアップし、安全に保管してください。
これが、万が一のトラブルから事業所を守る最後の砦です。
導入・教育の計画
新しいソフトを導入しても、職員が使いこなせなければ意味がありません。
現場の混乱を防ぎ、スムーズな定着を実現するためには、丁寧な導入・教育計画が重要です。
【導入スケジュールを決定し、社内へ共有する】
データ移行、研修、本稼働開始日などを含めた全体のスケジュールを作成し、全職員に共有します。
【職員への研修会や勉強会を実施する】
ベンダーによる導入研修会を設定します。役職や業務内容に応じた複数回の研修を実施するとより効果的です。
【新旧ソフトの併用期間を設け、徐々に移行する(1〜3ヵ月が目安)】
可能であれば、1〜3ヵ月程度の併用期間を設けるのもよいでしょう。最初の請求業務は新旧両方の介護ソフトでおこない、結果を照合することで、安心して新しい介護ソフトへ移行できるからです。
このように、介護ソフトの乗り換えは、
- ステップ①:【準備】現状課題を洗い出し、乗り換えの目的を明確にする
- ステップ②:【選定】自分の事業所に合うソフトを比較検討し、決定する
- ステップ③:【実行】データ移行と導入・教育の計画を立てる
上記、3つのステップで計画的に進めることで、失敗のリスクを大幅に減らせます。
特に、自分の事業所の課題を明確にし、それに合った介護ソフトの客観的な選定が成功への近道です。
介護ソフトの乗り換えに関するよくある質問(FAQ)

ここでは、介護ソフトの乗り換えを検討する際に、よくある質問とその回答をまとめました。
- Q. 乗り換えにかかる費用は、総額でどれくらいみておけばよいですか?
- Q. データ移行に失敗するリスクが心配です。どうすればいいですか?
- Q. 国の補助金は利用できますか?
順番にみていきましょう。
Q. 乗り換えにかかる費用は、総額でどれくらいみておけばよいですか?
A. 乗り換え費用の総額は、介護ソフトの価格体系や事業所の規模によって大きく変動します。
月額料金の安さだけで判断せず、以下の費用を含めた「トータルコスト」で比較することが重要です。
【初期費用】
介護ソフトの導入時に発生する費用です。数万円から、高機能な介護ソフトでは数十万円になる場合もあります。
【月額利用料】
毎月発生する費用です。利用者数や職員のアカウント数に応じて変動するプランもあります。
【データ移行費用】
見落としがちですが、重要な費用です。ベンダーによっては、別途料金が発生する場合があります。他社ソフトからの移行は、特に費用や対応範囲の事前確認をしましょう。
【ハードウェア費用】
クラウド型ソフトであれば、多くの場合、新たに専用のハードウェアを購入する必要はありません。インターネットに接続できるパソコンがあれば、利用できるものがほとんどです。
一方で、オンプレミス型(サーバー設置型)も、現在では専用サーバーを必要とせず、一般的な性能のパソコンで運用可能なケースが増えてきています。
このように、提供形態だけで必要な機材を一概に判断することは難しくなっています。そのため、検討しているソフトが現在お使いのパソコンで問題なく動作するのか、必ず各ベンダーに「動作環境」を詳細に確認することが、最も重要なポイントです。
Q. データ移行に失敗するリスクが心配です。どうすればいいですか?
A. データ移行は乗り換えにおける最重要課題です。
もちろん、失敗は避けなければなりません。
リスクを最小限に抑えるポイントは、次の2点です。
【実績豊富なベンダーを選ぶこと】
他社ソフトからのデータ移行実績が多いベンダーは、移行時のトラブル対応にも慣れており安心です。事前に実績を確認しましょう。
【事前のバックアップを徹底すること】
万が一の事態に備え、既存ソフトの全データを複数の方法(USBメモリ、外付けHDDなど)で必ずバックアップしてください。
移行完了後には、新旧両方の介護ソフトで利用者数名分のデータをランダムに抽出し、情報が正しく移行されているかを目視でチェックすることも重要です。
Q. 国の補助金は利用できますか?
A. はい、活用できる可能性があります。
代表的なものに、経済産業省の「IT導入補助金」や、各都道府県が実施する「介護テクノロジー導入支援事業」などがあります。
これらの補助金を活用すれば、介護ソフトの導入コストを大幅に削減できるでしょう。
ただし、申請には期間や要件が定められており、手続きも複雑な場合があります。
検討しているソフトが補助金の対象となるか、ベンダーに相談してみましょう。
介護ソフトの補助金制度に関するさらに詳しい情報は、下記の記事をご覧ください。
関連記事:介護ソフト補助金【最新】制度の種類・申請方法・採択ポイントまで徹底解説
【まとめ】介護ソフトの乗り換えは、事業所の未来を創る重要な一歩

この記事では、介護ソフトの乗り換えで失敗しないための理由、タイミング、そして具体的な3つのステップを解説しました。
介護ソフトの乗り換えは、決して簡単なものではありません。
しかし、それは単なる介護ソフトの変更ではなく、職員の働く環境を改善し、ケアの質を高め、事業所の未来をより良くするための「未来への戦略的な投資」です。
現状の課題から目をそらさず、正しい手順で一歩を踏み出せば、その先には必ず、今よりも明るい未来が待っています。
乗り換えを成功に導く介護ソフトなら「ファーストケア」
「乗り換えの重要性はわかったが、やはりデータ移行や導入後の運用が不安……」
「どの介護ソフトが本当に自分の施設に合うのか、決めかねている……」
もし、そのようなお悩みをお持ちでしたら「ファーストケア」にご相談ください。
日々の「請求・記録・計画書」作成の効率化はもちろん、乗り換えで最も不安な「データ移行」と「導入後のサポート」まで、安心してお任せいただけます。
さらに、介護保険制度に精通した専門スタッフが、貴事業所の円滑な移行を全面的にサポートします。
「パソコンが苦手な職員でも直感的に使える」と評判のシンプルな操作性で、導入後の現場の負担も最小限に抑えます。
貴事業所の課題やご予算に合わせた最適な乗り換えプランを、専門スタッフがご提案いたします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。